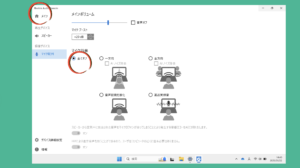教育には何ができないか
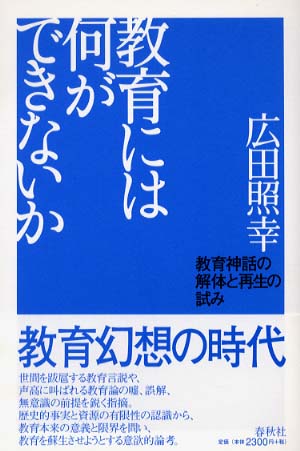
2003年初版の古典
2025年からさかのぼると、すでに20年以上も前の書籍であるにもかかわらず、本書で指摘されている「教育の限界」についての議論は、いまだに避けられ続けています。その結果、教師の不足という深刻な問題が社会を騒がせていることは、多くの人が感じていることでしょう。では、なぜこのような状況になってしまったのでしょうか?
この本では日本における学校教育の歴史を振り返りながら、「小さな大人」として育てられてきた子どもたちが、近代の学校教育によってどのように変化してきたのかを考察しています。そうした曲の歴史からも教育には限界があるという認識の重要性を説いています。
令和の時代になっても、〇〇教育は増え続け、教育の限界について語られることはほとんどありません。最近では、教員の「勤務時間」に関する議論が進み、残業代のない曖昧な労働環境が問題視されるようになっていますが、それでも学校に求められる役割や期待は増す一方のようです。
また、「教育万能主義」という概念からも教育の限界に触れています(松田1973)。日本では、なぜ「教育は万能である」と信じられ続け、青少年による残虐な行為は「教育の失敗」と見なされるのでしょうか。この本ではその背景にある考え方を丁寧に掘り下げています。
文科省の掲げる「誰一人取り残すことのない教育」は可能か?
20年が経ち、元号が令和になり、「誰一人取り残すことのない「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」という目標が文科省から掲げられとは筆者は想像したでしょうか。
この本にある教育の限界を十分に理解し、一方で「誰一人取り残すことのない教育」を実現することははたして可能なのでしょうか?これは教育者にとって大きなテーマです。